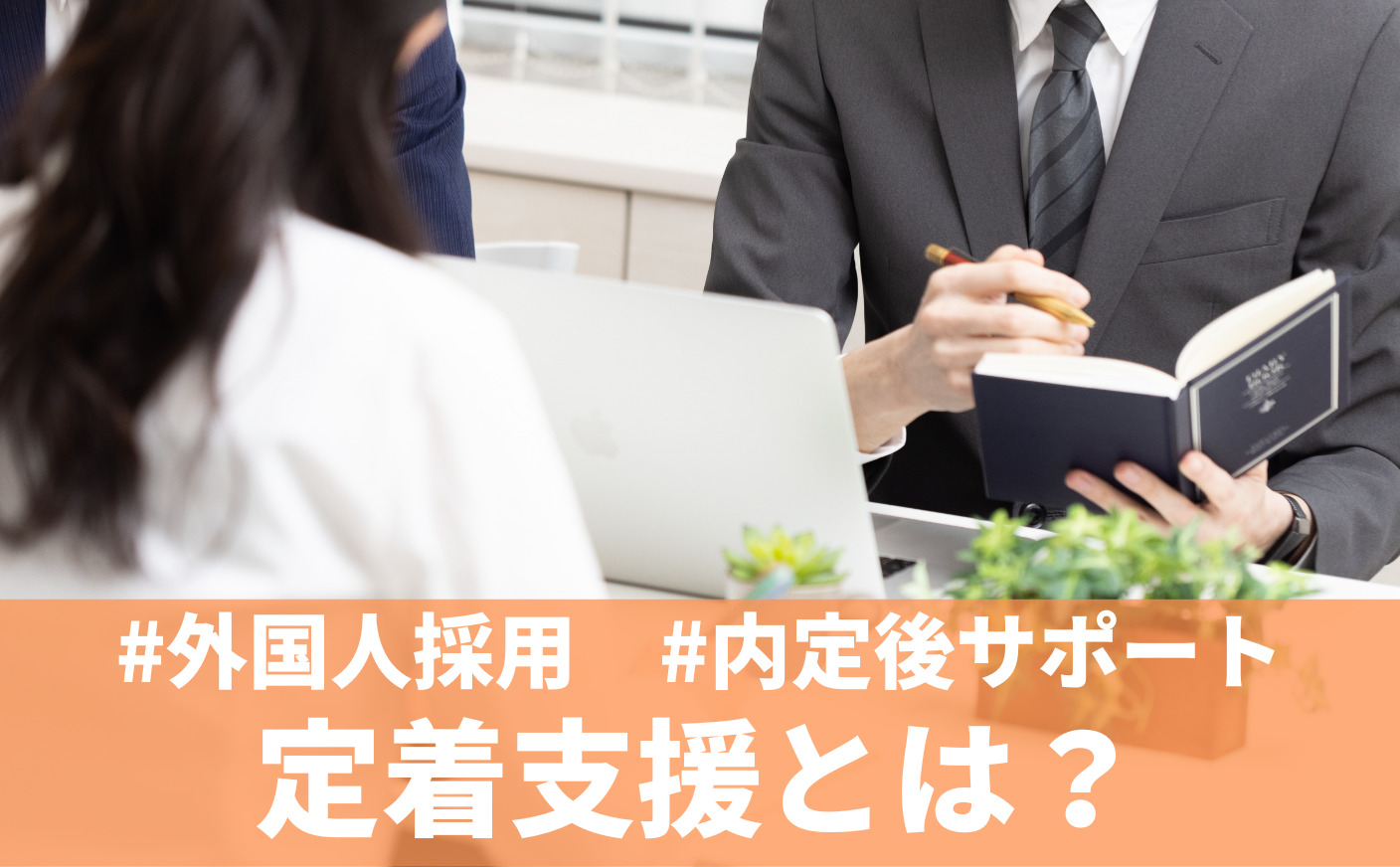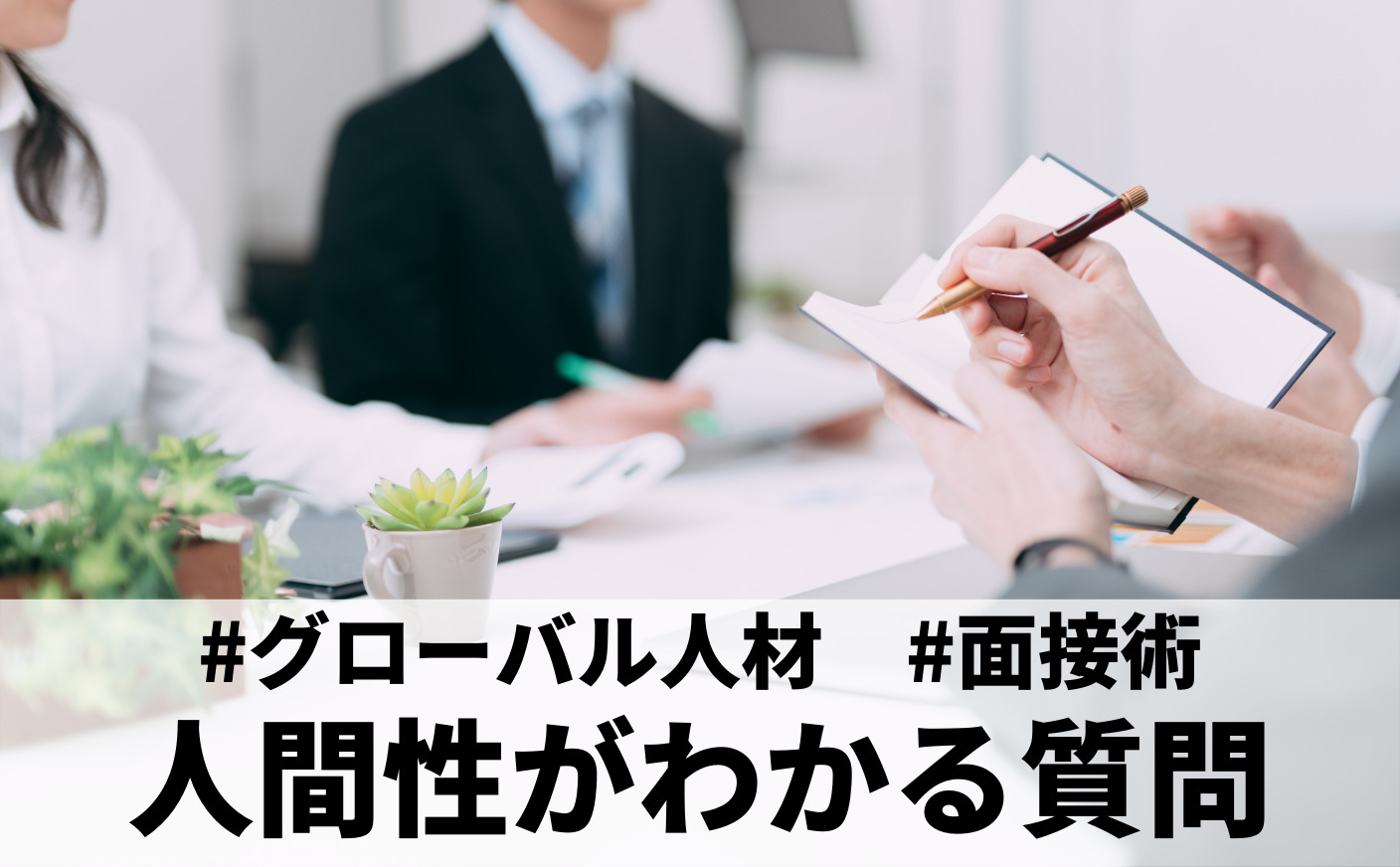ベトナムでは日本語教育・日本式教育が盛ん!?その背景とは?
Xin chào các bạn(こんにちはみなさん)!Sun*教育事業部の大原です。今回もご覧いただき、ありがとうございます!
以前、ベトナムの教育制度に関する記事で、義務教育について、数学に強いと言われる所以についてお伝えしました。
https://xseeds.sun-asterisk.com/education-20211125/
そちらでも少し説明しましたが、ベトナムでは第二言語として英語以外に日本語を取り入れている学校があります。多くの企業様から「ベトナムでは日本語教育は盛んに行われているんですか?」と質問をいただきますが、今回はそれにお答えいたします!
ベトナムではなぜ日本語に注目されているの?
実際、日本語を学ぶベトナム人は増えているの?
ベトナム人が日本語を学ぶ目的は?
そんな疑問をお持ちの方にぜひ読んでいただきたい記事です。
なぜベトナム人は日本や日本語に注目?
ベトナム人の日本語学習者を対象としたアンケートによると、日本語を学ぶ目的は「仕事や就職の関係」「日本に留学したい」「趣味」「日本のことを知りたい」の4つが多く回答されています。
【参照先】ベトナムにおける 日本語教育の現状と日本留学の関係に関する研究
最も多い答えは「仕事や就職の関係」でしたが、日本だけでなくベトナムでも日本語が話せる人材が必要ということがわかります。ベトナムにはハノイ、ダナン、ホーチミンに日本商工会議所があり、2020年末時点で約2000社が加入しています。アセアン諸国へ進出した日本企業のうち、ベトナムへ進出した日本企業数が2018年に第1位となりました。その後も1位を継続しています。ベトナムへの投資額は2018年のデータによると日本は83億4,305万ドルで1位で、2年連続1位という結果です。日本からの投資件数は3年連続で増加しており、2018年に過去最高を更新しました。日本もベトナムに注目していることが見て取れます。過熱していくベトナムでの日本語教育は、こういった経済的背景が大きく関係してることがデータからもわかりますね。
【参照先】ベトナム進出の日本企業数についてベトナムの日本語学習者数の伸び率は世界一(ベトナム語)
日本における在留ベトナム人の推移
次に、日本での在留ベトナム人の推移を見ていこうと思います。
上のグラフを見てわかる通り、在留ベトナム人は年々増加しています。現在在留外国人の国籍で最も多いのは中国です。ベトナム人は2019年までは2位だった韓国を2020年に抜いて2位となりました。技能実習生の増加がこの結果に大きく影響していますが、ホワイトカラーといわれる高度人材枠でもベトナム人の日本への進出が顕著です。
留学技能実習生技術・人文知識・国際業務その他総数総数227,844383,248283,2591,929,2142,823,565中国106,09958,02186,562494,729745,411韓国9,32111224,378382,578416,389ベトナム51,337220,55664,093114,060450,046
ちなみに、Sun*が教育を提供しているxseedsの対象学生たちは、「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーに属し、日本で就労しています。
【参照先】ベトジョー:日本の在留ベトナム人数44.8万人、韓国抜き国籍別2位に
ベトナムにおける日本語学習者の増加
2015年および2018年の国際交流基金(ジャパンファウンデーション)の調査によると、日本語学習者数、増加率は以下の通りです。
2015年学習者数2018年学習者数増加率中国953,2831,004,625105%インドネシア745,125709,47995%韓国556,237531,51196%オーストラリア357,348405,175113%タイ173,817184,962106%ベトナム64,863174,521269%
2018年のデータを見ると、海外の日本語学習者は、中国、インドネシア、韓国、オーストラリア、タイに次いで6番目に多く、ベトナムはまだまだ少ない印象を受けます。ですが、前回の2015年の調査結果と比較すると、ベトナムの日本人学習者数の伸び率は世界的にみても1位となっています。学習者数上位国がほぼ横ばいの伸び率に対して、ベトナムのこの結果から、それだけ日本や日本語への注目度の高さが伺えますね。また、上に挙げた国別の、新型コロナ流行前2019年12月に行われたJLPT受験者数は以下の通りです。
2019年12月実施JLPT受験者数中国133,082インドネシア16,211韓国36,997オーストラリア1,504タイ13,014ベトナム41,151
日本語学習者数のみに注目すると他国と比較した時に少ない印象を受けますが、JLPT受験者数は世界2位となっています。これはおそらく技能実習生によるギャップで、彼らは送り出し機関で日本語教育を受けているため、日本語学習者として数字に反映されていないと考えられます。次に、ベトナムにおける学習者の属性は以下の通りです。
初等、中等、高等教育においての日本語学習者ですが、上の表には所属機関の正規科目として学習している人以外にも、課外活動として日本語を学んでいる人も含まれています。学校教育以外というカテゴリーは、民間の日本語学校や技能実習生の送り出し機関などが該当します。圧倒的に割合が高くなっているのは、技能実習生が多いことが第一の理由です。以前は日本語を学ぶ環境がなかった地方都市でも、ベトナムに帰国した元技能実習生や元留学生などが地元で日本語教育を提供するということも増えています。確かに、私もハノイで日本語を話すベトナム人に出会うことも多く、「どこで日本語を勉強したのですか?」と尋ねると、技能実習生として日本で仕事をしていた人がほとんどです。日本語教育機関や日本語教師の数も、元技能実習生の増加によって今後ますます増えることが予想されますね。
【参照先】国際交流基金:2018年度 海外日本語教育機関調査JLPT:実施国・地域別応募者数・受験者数ベトナムにおける元技能実習生日本語教師の現状と問題点
ベトナムの小・中・高校での日本語教育
冒頭でもお伝えしましたが、2016年にベトナム政府は第二言語として英語以外に日本語を取り入れることを決定し、2021年2月時点で63省市のうち10省市において日本語教育が行われています。
【参照先】在ベトナム日本大使館
日本語教育に留まらず行われている『日本式教育』
注目されているのは「日本語教育」だけではなく、マナーの習得、自立の促進、日本の道徳心等を養うことを目的とされた「日本式教育」も挙げられます。世界には多くの日系幼稚園が存在しますが(ここベトナムにも、ハノイに5ヶ所、ホーチミンに6か所あります)、主に現地の子どもたちを対象とした日本式小学校はほとんどありません。その一つがベトナムハノイにある「日本国際学校(JIS)」です。※ちなみに、私が調べた限りでは2022年1月時点でエジプトにあるエジプト日本学校、カンボジアにあるCIESF Leaders Academy、JISの3校が海外にある日本式教育を行っている小学校です。
【参照先】JICA 「日本式教育」で、子どもたちが変わる!CIESF Leaders Academy
JISは、幼稚園の年少児から高校2年生(今後高校3年生まで設置予定)までが通う日本式インターナショナルスクールです。学生は99%がベトナム人で、日本の文部科学省が定める学習指導要領に沿ったカリキュラムを日本語で提供しています。入学当初はまったく日本語ができない学生も多いのですが、日本語という語学を学びながら日本の教科書に沿って算数や技能教科(音楽や体育など)も学び、高校卒業までにN1を取得する学生もいます。JISでは日本語ができる学生を育てるだけではなく、日本式の道徳の授業にも力を入れており、上にも書いた通りマナーの習得、自立の促進、日本の道徳心等を養うことも目的としています。一般的なインターナショナルスクールのイメージは、母国語や公用語が英語ではない国にある、英語で授業が行われる学校というものだと思いますが、日本語のインターナショナルスクールで日本人学校以外の存在となると大変珍しいです。JISで働く先生にお話を伺ったところ、「JISに子どもを通わせているのは、その子に日本式のマナーや道徳心を持ってほしい、将来日本に留学や就職してほしいという強い思いが親御さんにあるから」とのことでした。JISに通う生徒の親の中で日本語を話せるのは、その先生のクラスで見ると生徒19人中3人のみで、自分自身は日本語も日本式教育も知識がないけれど、ぜひ子どもには習得してほしいという思いがあるようです。また、JISの高等部を卒業後は、100%の学生が日本にある大学に進学を希望しています。それを実現するためにJISは複数の日本の大学との提携を進めており、一期生(現在高校2年生)の卒業とともにJIS出身の留学生が日本へ羽ばたいていく予定です。それだけ日本式教育が注目されているということですね!
終わりに
いかがでしたか?今回は、ベトナムの日本語教育、日本式教育事情についてお届けしました!日本語教育、日本式教育がベトナムでは積極的に行われています。教育からもわかるようにベトナムは日本を向いており、また、JETROのデータから日本がベトナムを向いていることもわかり、より強い両国の関係性を目指していることが理解できます。今後も日本語教育の需要は増えることが予想され、渡日するベトナム人も増えるのではないかと思います。
私たちSun*も日本就職を目指す学生のサポートを今後も引き続き行っています!わたしたちの事業の内容やxseeds Hubに関してのお問い合わせなどはこちらからお願いします。また、Facebookページをフォローしていただくと、記事更新の通知だけではなく、Facebookでしか見れない#日常の一コマをご覧いただけます。ぜひ覗きに来てください。それでは次回の更新をお楽しみに。Hẹn gặp lại nhé!(また今度)