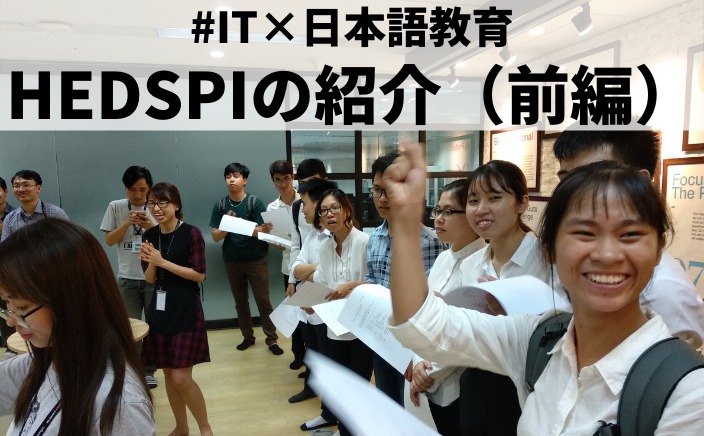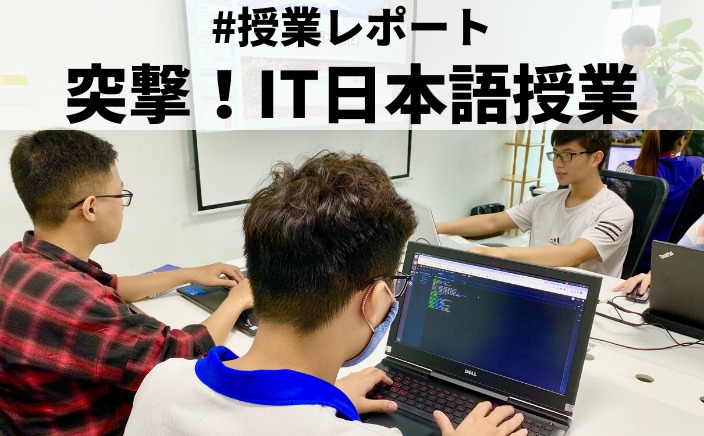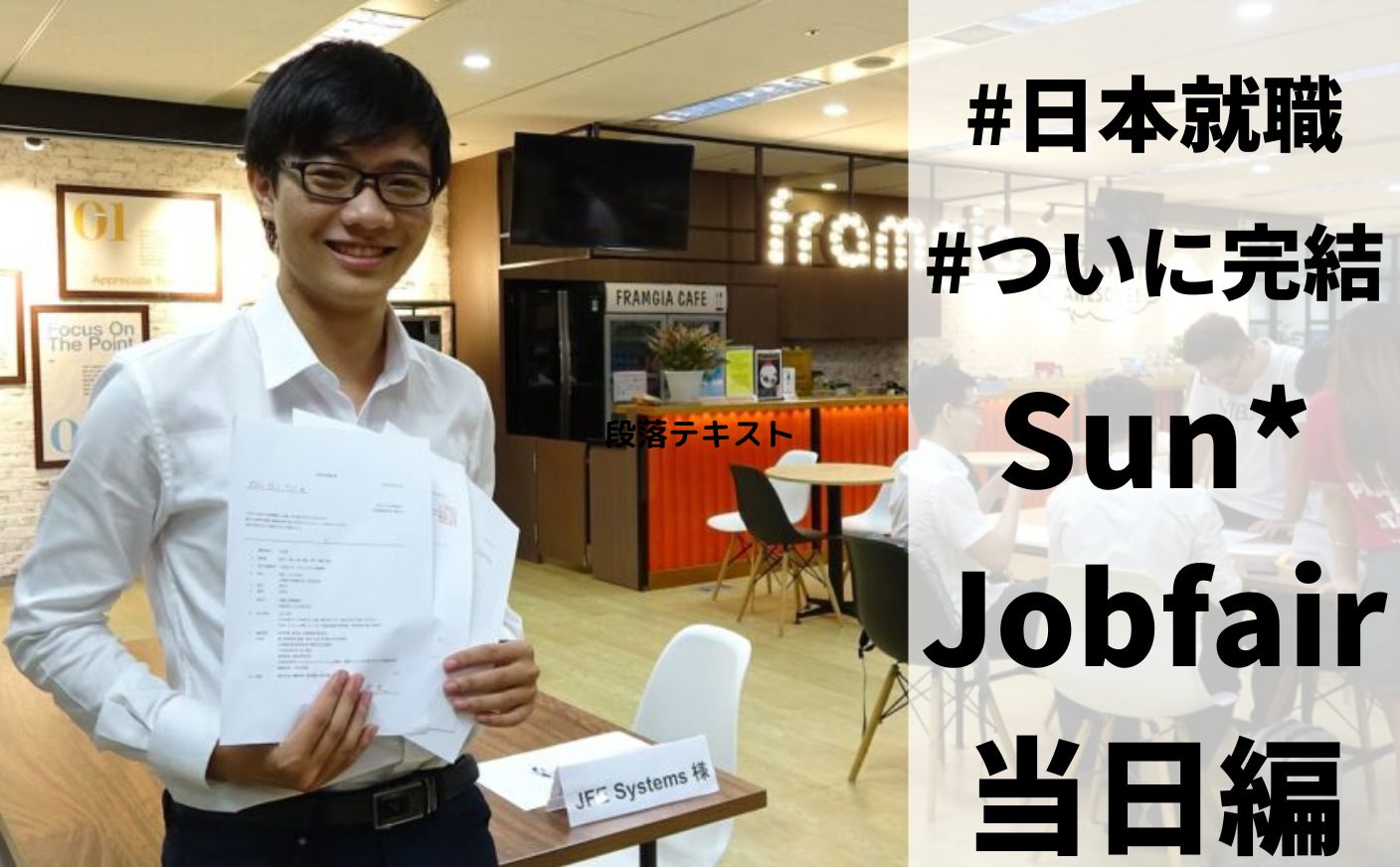About xseeds
xseeds(エクシーズ)とは、グローバルに才能の発掘、教育、最適配置を行い
未来のイノベーターを輩出する教育プロジェクトです。
わたしたちは、世界中の才能の種を探し、光をあてることから始めました。
そして、これまでの事業やプロダクト開発で培ったノウハウとこれからのトレンドを反映した
独自カリキュラムを活用し、自身で未来を切り開くことができるよう、蕾になるまで導きます。
さらに彼らが才能を開花し価値創造できる最適な場所を見つけ、送り出していきます。
様々な要素 "x"と才能 "seeds"をかけ合わせ、未来のイノベーターを輩出し、
世界にポジティブなアップデートを起こす価値創造人材を創出するための仕組み
わたしたちSun*は、これをxseeds(エクシーズ)と名付けました。
わたしたちは、世界中の才能の種を探し、光をあてることから始めました。 そして、これまでの事業やプロダクト開発で培ったノウハウとこれからのトレンドを反映した
独自カリキュラムを活用し、自身で未来を切り開くことができるよう、 蕾になるまで導きます。
さらに彼らが才能を開花し価値創造できる最適な場所を見つけ、 送り出していきます。
様々な要素 "x"と才能 "seeds"をかけ合わせ、未来のイノベーターを輩出し、 世界にポジティブなアップデートを起こす価値創造人材を創出するための仕組み わたしたちSun*は、これをxseeds (エクシーズ)と名付けました。、